04.30.2006 |
 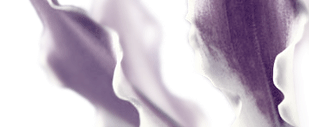 |
悲しみについて
死は発生と進行形を排除した超越内容であるにもかかわらず必然的であるかのように私達へ迫りくる絶対の形式です。それは私達を境界付ける階梯でありながら、永劫に言及を許さないものです。 だから死に面前すると私達はいつも会話の可能性や自己との接点とを暴力的に隠蔽し、非論理的な完結によって思考を圧殺して、不可視の傷を慰めようとします。そこで蒙昧で反知的な所作や理なき文学的趣味に形容不可能なディレンマの放出・解消を委ねてみても、それが人の性を退行させる弥縫策でしかないために、事後に罪悪に苛まれてしまいます。人は必ず『人類』へと回帰することを忘れては、このままずっと無為の文脈を超えられないことでしょう。自己を未定義にするということが他者への侮辱であることを知らない者に発言や生は賦与されません。 自己の死は他者へ自由を与えますが、他者の死の記述は自己へ自己の枷を与えます。古典的な意味でファルスの喪失は自己瓦解の合図です。それを必死にくい止めようと試みる時、私達はどこへ何を問えば良いのでしょうか。何を思い、何を想えば良いのでしょうか。
過ぎていくことが忘却ではなく、悲しみの増大になる時、初めて私達は創られた傷口に結節点を設けることができるのではないでしょうか。 分かりきった答えを問いへと再度配置する。それを禁止してばかりでは私達の生はまた空虚に満充するだけではないでしょうか。
他者はいつも自己をすり抜ける支配不可能な自由者でありながら、その永逝による不在化は選択域の拡大によって自己を不自由にしてしまう両義者です。もちろんこのディレンマは日常の越権によって起きる誤謬ですが、この誤謬は悲しみを伴う以上、単なるミスリードではありません。他者の死によって産まれる『悲しみや寂しさ』は『孤独』を指し示します。つまりその情動とは心が閉じた臨在・システムであることの証左であり、免疫機能の表れなのです。 悲しみによる自由の再確保によって「他者の死」は「自己の死」と同等化され、悲しみよる反省によって私達は自己の本来的な様相を取り戻します。一時の享楽等によって悲しみを黙殺することから再度逃げる時、私達は社会形式に意義を取り戻すことができるのです。 私達がかろうじて『私』を純化できるのは、至上の自己浄化である悲嘆の真意を知っているからなのです。
|
2006年4月30日_‡‡
ayanori[高岡 礼典] 私の音なき声はどこへ届くのでしょうか。
|